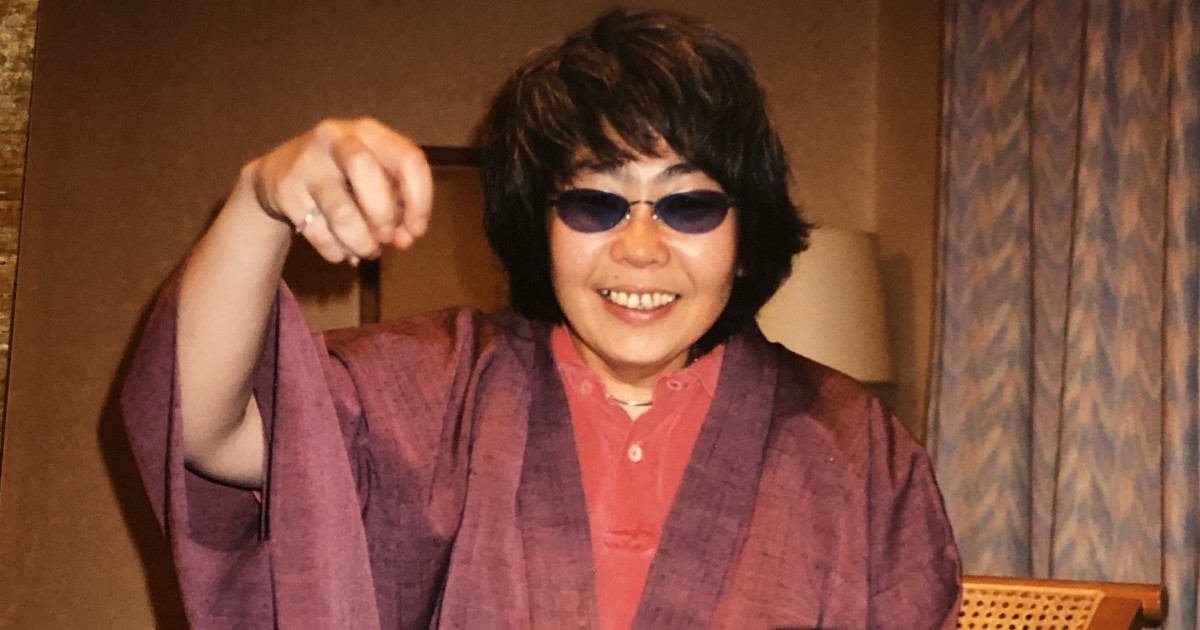柴崎友香『わたしがいなかった街で』
今ここにいる自分は他のどこにも存在しない。今ここで起きていること以外の出来事を、自分は今ここで知ることはない。今ここにいる自分は、両親とそのまた両親とそのまた……連綿と続く血のどれが欠けても現存することはない。そんな当たり前だけれど、普段めったに考えないような、その意味ではもしかしたら「当たり前」ではないのかもしれないことを、意識の表面に浮かび上がらせ、「わたし」という存在の不自由さとかけがえのなさに気づかせてくれるのが、柴崎友香の『わたしがいなかった街で』だ。
主人公の〈わたし〉は平尾砂羽三十六歳。商社の子会社で契約社員として働いていて、一年ほど前に離婚を経験している。近所に住んでいる友人・有子とその五歳の息子・昇太、大阪にいた頃通っていた写真のワークショップで知り合った中井、契約社員仲間の加藤美奈といった人々との交流はあるものの、砂羽はいわゆる「リア充」と呼ばれるような生活は送っていない。休みの日にもっとも時間を費やしているのは、戦争や内戦のドキュメンタリー映像を繰り返し見ること。有子の父親から、そんなものを見るのは暇だからであって〈ほんとに大変だったら、他人の大変なのまで見たくないじゃない〉と意見されるのだけれど、そんなことは砂羽にもわかっている。でも、映像の中で殺されている人や殺している人のことを「なぜ、自分ではないんだろう」と考え、〈日常という言葉に当てはまるものがどこかにあったと〉すれば、それは穏やかな生活の中にあるのではなく、戦争で破壊された世界を〈目撃したときに、その向こうに一瞬だけ見えそうになる世界なんじゃないかと思う〉砂羽は、有子の父親が言うほど不健全なんだろうか。わたしにはそう思えない。
原爆の投下目標だった橋の近くのホテルで、一九四五年の六月までコックをしていた祖父のことを思い、もし祖父がホテルで働き続けていたら、今ここにいる自分は存在しなかったんだと思う砂羽。iPhoneで作家・海野十三が書いた六十五年前の日記を読んで、自分が住んでいた場所がかつて空襲で焼け野原になったことを知り、その光景を今ある街の景色の向こうに見ようとする砂羽。〈もうない場所、行けない場所、会えない人、会うかもしれない人、どこかにいる人〉に思いを飛ばす砂羽。風景と時間が積もり重なって、「今」と「ここ」があることに気づく砂羽のことを、わたしは、自分なんかよりずっと考えが深い人だと尊敬する。人と話したり、出かけたり、働いたり、過去のことを思い出したり〈それらが全体として現在の「自分の生活」と把握できるような形に組み上がっていなくて、ただ個々の要素のまま、行き当たりばったりに現れ、離れ、ごみのようにそこらじゅうに転がっている〉と感じてしまう砂羽のほうが、日々の仕事や雑事に押し流されている自分なんかよりずっと生活に対して姿勢が良いと感心する。